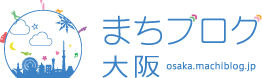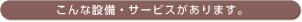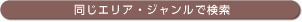スタッフブログ
- 情報
- 投稿日:2016/05/02
思いっきり生きる ドクター長堀優氏
「思いっきり、生 き る」
育成会横浜病院々長 長堀 優 氏
1. 死は敗北ではない
*いま世の中は、「健康情報」であふれ返っている。「健康で生きる」とは、一体どうい
うことなのか。医療や食品に頼ることではなく、自分自身の生き方を見つめ、そして考
え直すことだ。つまり、健康な生き方のカギを握るのは他ならぬ自分自身なのだ。
一方で、最近、医療への批判が高まり、殊にがんに対する手術、抗がん剤療法などへの
批判が増えている。現代医学の中心である西洋医学は、ひどい怪我や肺炎、虫垂炎など
の炎症には欠かせないもので、本来、重要なものだ。ただ、この日本では、あまりにも西
洋医学に頼り過ぎており、その結果、様々な矛盾を起こしているのも確かだ。
*体力のない患者に手術を施したり、強い抗がん剤を投与するなどは、矛盾の例と言える。
この背景には、西洋医学の「死は敗北なり」との考えがある。死は本来、誰にでも訪れる
もの。しかし、西洋医学では、この死との向きあい方を全く考えてこなかった。ここに大
きな問題がある。だからこそ、近づく死を遠ざけようとムリな治療が行われてしまうのだ。
死は誰にでも100%訪れる。だが西洋医学の現場では、「敗北」である死を考えないように
してきた。私も若い時、そう思っていた。しかし、ある時、「死は敗北ではない」という
ことに気づかされた。
*教えてくれたのは、死を目前にした勇気ある患者さんたちだった。恐ろしいはずの死を
とことん見つめることで、現在の「生」「命」が輝き、それが「健康に生きる」につなが
っていく…。正に、「大どんでん返し」だ。このように「死は敗北ではない」と教えるの
が実は東洋哲学であり、西洋医学の至らないところを、補ってくれているようだ。
*ところで、今の西洋医学のどこに問題があるのか。世界は相反する2つの要素、善と悪、
光と影、粒子と反粒子…からできている。この考え方が二元論で、これによれば当然、病
気は「悪」となる。悪である病気を治そうとして、医学が進歩してきたのは確かだ。
ところが実際には「病気になって生き方の間違いに気づけてよかった」という患者さんが
おられる。「万事塞翁が馬」という言葉があるように、東洋では善も悪も本来分けがたい
ものという考え方がある。したがって病気も悪いばかりではないのだ。そこで西洋科学と
東洋哲 学の統合という発想が生まれた。これが究極の一元論であり、医療のみならず、
これからの世の中を変えていく - そう私は思っている。
*いま現代医学の中心は西洋医学だが、ここまで進歩させたのは科学の力だ。我々はどうし
ても従来の常識に引っ張られてしまう。しかし、事実を先入観なしに眺めること、この姿
勢の中にこそ常識を打ち破る考え方を生む。事実を観察し → 仮説を立て一般化する →実
生活に応用する、これが科学の方法。しかし、ここで注意しなければいけないのは科学的
方法を重視した医学の世界と、実際の現場の医療は食い違うことも多いということ。実は
これこそがいまの医療の現場における大きな問題の一つだ。
*西洋科学に基づく医学の世界では、客観的観察と一般的な法則の2つが重要になってくる。
例えば、検査で悪い所を見つけるのは、客観的観察に当たるだろう。「この病気にはこん
な薬がよい」は一般的な法則。誰にも分るような客観的な検査データや多くの人に効く治
療法は、医学でもちろん大切だ。しかし、その一方で実際の医療の現場では、目の前の患
者が何を悩んでいるかが重要になる。例えば、レントゲンの検査結果は患者の期待とは、
必ずしも一致しない。治療法についても同様だ。治る人もいれば治らない人もいる。皆、
経過は違う。万能薬といったものは存在しない。しかし、医者は、医学的で科学的な立場
を大切にする。従って、患者に向かって「生存率は何パーセントです」と平気で言う医師
もいる。しかし、「自分はどうなるのか!?」という患者の問いには、答えてはいない。
医師には患者個人のことより、一般的傾向や法則が大事なのである。
*医師がそのような患者個人の訴えより、客観的な検査データや一般的傾向を大事にするの
は、先述の「科学的態度」とピタリと一致する。医師のこの態度が変わらなければ、医師
の思いと患者の希望や訴えとは永遠に噛み合うことはない。この点を作家・遠藤周作氏は
「現場の医療とは、『医学+人間学』」と喝破しているが、正にその通り。ここで謂う人間
学とは「人間のこころ」ではないか。
*このような西洋医学だが、はっきりとした特徴と限界がある。急に症状が起こってくるよ
うな、「急性期疾患」には大きな威力を発揮する。怪我、肺炎、虫垂炎、心筋梗塞には、
いい結果が出ている。その一方、「慢性期疾患」、糖尿病、高血圧など生活習慣にかかわ
る病気や進行した「がん」、精神科の病気、膠原病などの所謂「難病」に対する治療は、
いまだ道半ばだ。「病気を治すということが薬を必要としない状態に戻すこと」とするな
ら、「病気を治す」ことは全くできていない。表面的な症状を抑えているだけだ。「5年
生存率」という言葉がよく使われるが、がんの余命宣告など、本来、医師にはおこがまし
くてできることではない。
2.「どんでん返し」
*「心が体に影響を与える」と言えば、意外に思うかもしれない。心は目に見えないので科
学的ではないようにも思えるからだ。しかし、医学界ではこれを当たり前のこととして認
めている。医学界には、「プラシ―ボ効果」という言葉がある。砂糖水を薬として飲むと
頭痛が治るといった現象を指す。心が体の反応を変えているのだ。「プラシーボ」とはラ
テン語で「喜ばせる」という意味だ。
医師と患者の信頼関係が良好で、患者自身の「治す」という思いが強くなると、「プラシ
ーボ効果」が、ますます高まることがわかってきた。何より「副作用がない」というのが
大きなメリットだ。われわれ医療者は、このプラシーボ効果を今一度、見直してみる必要
がある。この「プラシーボ効果」とは逆の「ノーシーボ効果」というのもある。これは
「否定的な思いが病気を引き起こす」という現象である。「自分は心臓病に罹り易い」と思
っている女性は、そうでない女性の死亡率の4倍もあるという。
*2500年前、仏陀は「すべての人間は、自分自身の健康、ないしは病気の作者である」
と説いた。また、「ポジティブな思いは、良い遺伝子のスイッチを入れる」と指摘するの
は村上和雄・筑波大名誉教授だ。「 ポジティブな思いとは、他人への思いやり、つまり利
他の心である。この時のワクワクする気持ちが大切であり、行動を選ぶ時は、正しいか、
正しくないかより、嬉しいか嬉しくないかで選ぶべし 」と。一方、エゴや欲、怒りや不安
にとらわれた行動は、その対極と言える。そのような思いは、自分の心に悪い遺伝子のス
イッチを入れる。つまりは、良いも悪いも自分次第ということになる。がんに関して言え
ば、ポジティブな思いは「良い遺伝子」で、がん抑制のスイッチを入れる。ネガティブな
思いは、逆に、がんのスイッチが入りやすい。
*鈴木秀子・聖心女子大学元教授は、心の健康を回復させる特徴として、3つのポイントを
挙げている。➀運命を受け入れること。私たちを生かす大自然に感謝し、すべてを委ね、
何があろうとも受け入れることだ。➁生きていることは当たり前ではない。人生はたいへ
んなことを自覚し、生かされているという奇跡に感謝し、生きる意欲に溢れ、毎日を送る
こと。➂他人や自分への愛を感じること。人とのつながりを大事にし、人に尽くしたいと
いう強い願望を持つこと。この3つの態度が心を健康にする、鈴木先生は指摘している。
言いかえれば、「運命の受容」「生かされていることへの感謝」「他人への愛」というこ
とになる。それが人生を実り多いものにする秘訣ではないか。悔いなく、思いきり生きる
ことができれば、最後の時期を迎えてもても、受け入れることができる。良く生きること
は、良く死ぬことでもある。
*科学の巨人たちが遺した言葉を紹介したい。アインシュタインは「私たちが最も美しく、
最も感動をするのは神秘的なものを感受した時である。そして、これこそがすべての科学
の原動力である」という言葉を遺している。ノーベル賞を受賞された山中先生と益川先生
が対談で話されたのは、「人間の考えることなんかより、自然の方がずっと奥深い。そし
て、考えるとは、感動することである」と。このように科学の巨頭たちが揃いも揃って、
知識や理性より情動の重要性を説いているのは、驚くべきことだ。考えて見れば、情動、
感動という言葉はあっても、知動、理動という言葉はない。自分の感性をもっと大事にし
た方がいい。私の今の思いを言葉で表せば、医療現場では平均化より個別化、言いかえれ
ば「一人ひとりの個性の違いを大事にする」ことである。心の持ちようで、体や病気が変
わるのだ。したがって、今後の医療を考える時、「個別化医療」と「心を見つめる医療」、
この2つがキーワードになってくると私は思う。
*がんの医療においては、医療者と患者に加え、患者の家族を加えた三者の関係を良好に保
つことが重要になる。問題はがんが再発したり、進行した状況になった時である。医療者
は痛みを取るなどの対症療法しかなく、次第に腰が引けていく。その一方、家族は、別離
思いに苛まれ、セカンド・オピニオン探しなどに追われ、患者との対話も次第に少なくな
る。そんな中で患者は自分の状態が悪くなっていくことをはっきり自覚し、後悔の念に苛
まれたりする。そして何より、家族と共に最後の時を長く分かち合いたいと強く望むよう
になる。しかし、その一方、家族に心配をかけまいと自らの殻に閉じ籠り、つらい孤独の
中で最後を迎える人が少なくない。
*最近、セラピストの資格を持つ看護師が大きな役割を果たしている。ターミナルケアの逃
げようもない精神的に過酷な現場で疲弊し、現場を辞めた看護師が自分を癒すために、ア
ロマなどの資格を取って、看取りの現場に復帰する人が増えてきたのは嬉しいことだ。こ
のような看護師とのセラピーを通じた触れあいで、どうしようもない不安を癒されたとい
う患者を多く見てきた私は、このような精神と技術をもった看護師に大いなる期待を抱い
ている。
*死と向き合うことで見えてくるものは何か。仏教は教える。死という深い悲しみをとこと
ん見つめることにより、実は大どんでん返しが起きる。それは何か。今生きていることは
当たり前ではない。感謝すべきこと。つまり、いま生かされているという奇跡への感謝に
他ならない。今日、平和で過ごせたことは、当たり前ではなく感謝すべきこと。この貴重
な毎日をワクワク楽しく暮らすことが旅立ちの日を、後悔なく迎えるための秘訣になるの
だ。さらに仏教では、「対峙ではなく、共存すべし」とも教えている。病気の原因となっ
た自分の考えや行動を見つめ直し、生活を改めること。悲しみの底から湧きおこってくる
「どんでん返し」とは、悲嘆の極致から、感謝、愛、受容の心によって、幸せな気持ちに
一気に上昇させることである。正に「どんでん返し」だ!
*神道にも「中今(なかいま)」という言葉がある。過去の後悔や未来の不安から離れ、今に集
中する。今には過去も未来もない。がんがあろうとなかろうと、誰にも平等に与えられた
死の瞬間・・・所詮、未来など誰にも分らない。健康であっても明日事故で命を落とすか
もしれない。それが人生だ。病気の人も健康な人も、与えられたこの今の一瞬を最良とし、
そして精一杯生きること、それが人生で大切なのだ。明日が来ること、それは「当たり前
」ではない。そのことをわれわれは肝に銘じる必要がある。仏教でいう「生き切る」と共
に、このような心境で人生を全うすること。これこそが究極の健康法ではないかと私は考
えている。 (了)
「思いっきり、生 き る」 育成会横浜病院々長 長堀 優 氏
1. 死は敗北ではない *いま世の中は、「健康情報」であふれ返っている。「健康で生きる」とは、一体どういうことなのか。医療や食品に頼ることではなく、自分自身の生き方を見つめ、そして考え直すことだと私は思う。つまり、健康な生き方のカギを握るのは他ならぬ自分自身なのだ。
一方で、最近、医療への批判が高まり、殊にがんに対する手術、抗がん剤療法などへの批判が増えている。現代医学の中心である西洋医学は、ひどい怪我や肺炎、虫垂炎などの炎症には欠かせないもので、本来、重要なものだ。ただ、この日本では、あまりにも西洋医学に頼り過ぎており、その結果、様々な矛盾を起こしているのも確かだ。
*体力のない患者に手術を施したり、強い抗がん剤を投与するなどは、矛盾の例と言える。この背景には、西洋医学の「死は敗北なり」との考えがある。死は本来、誰にでも訪れるもの。しかし、西洋医学では、この死との向きあい方を全く考えてこなかった。ここに大きな問題がある。だからこそ、近づく死を遠ざけようとムリな治療が行われてしまうのだ。死は誰にでも100%訪れる。だが西洋医学の現場では、「敗北」である死を考えないようにしてきた。私も若い時、そう思っていた。しかし、ある時、「死は敗北ではない」ということに気づかされた。
*教えてくれたのは、死を目前にした勇気ある患者さんたちだった。恐ろしいはずの死をとことん見つめることで、現在の「生」「命」が輝き、それが「健康に生きる」につながっていく…。正に、「大どんでん返し」だ。このように「死は敗北ではない」と教えるのが実は東洋哲学であり、西洋医学の至らないところを、補ってくれていると私は思う。
*ところで、今の西洋医学のどこに問題があるのか。世界は相反する2つの要素、善と悪、光と影、粒子と反粒子・・・からできている。この考え方が二元論で、これによれば当然、病気は「悪」となる。悪である病気を治そうとして、医学が進歩してきたのは確かだ。
ところが実際には、「病気になって生き方の間違いに気づいてよかった」という患者もいる。「万事塞翁が馬」という言葉があるように、東洋では善も悪も本来分けがたいものという考え方がある。したがって病気も悪いばかりではないのだ。そこで西洋科学と東洋哲 =1= 学の統合という発想が生まれた。これが究極の一元論であり、医療のみならず、これからの世の中を変えていく - そう私は思っている。
*いま現代医学の中心は西洋医学だが、ここまで進歩させたのは科学の力だ。我々はどうしても従来の常識に引っ張られてしまう。しかし、事実を先入観なしに眺めること、この姿勢の中にこそ常識を打ち破る考え方を生む。事実を観察し → 仮説を立て一般化する →実生活に応用する、これが科学の方法。しかし、ここで注意しなければいけないのは科学的方法を重視した医学の世界と、実際の現場の医療は食い違うことも多いということ。実はこれこそがいまの医療の現場における大きな問題の一つだ。
*西洋科学に基づく医学の世界では、客観的観察と一般的な法則の2つが重要になってくる。例えば、検査で悪い所を見つけるのは、客観的観察に当たるだろう。「この病気にはこんな薬がよい」は一般的な法則。誰にも分るような客観的な検査データや多くの人に効く治療法は、医学でもちろん大切だ。しかし、その一方で実際の医療の現場では、目の前の患者が何を悩んでいるかが重要になる。例えば、レントゲンの検査結果は患者の期待とは、必ずしも一致しない。治療法についても同様だ。治る人もいれば治らない人もいる。皆、経過は違う。万能薬といったものは存在しない。しかし、医者は、医学的で科学的な立場を大切にする。従って、患者に向かって「生存率は何パーセントです」と平気で言う医師もいる。しかし、「自分はどうなるのか!?」という患者の問いには、答えてはいない。医師には患者個人のことより、一般的傾向や法則が大事なのである。
*医師がそのような患者個人の訴えより、客観的な検査データや一般的傾向を大事にするのは、先述の「科学的態度」とピタリと一致する。医師のこの態度が変わらなければ、医師の思いと患者の希望や訴えとは永遠に噛み合うことはない。この点を作家・遠藤周作氏は「現場の医療とは、『医学+人間学』」と喝破しているが、正にその通り。ここで謂う人間学とは「人間のこころ」ではないか。
*このような西洋医学だが、はっきりとした特徴と限界がある。急に症状が起こってくるような、「急性期疾患」には大きな威力を発揮する。怪我、肺炎、虫垂炎、心筋梗塞には、いい結果が出ている。その一方、「慢性期疾患」、糖尿病、高血圧など生活習慣にかかわる病気や進行した「がん」、精神科の病気、膠原病などの所謂「難病」に対する治療は、いまだ道半ばだ。「病気を治すということが薬を必要としない状態に戻すこと」とするなら、「病気を治す」ことは全くできていない。表面的な症状を抑えているだけだ。「5年生存率」という言葉がよく使われるが、がんの余命宣告など、本来、医師にはおこがましくてできることではない。 =2= 2.「どんでん返し」 *「心が体に影響を与える」と言えば、意外に思うかもしれない。心は目に見えないので科学的ではないようにも思えるからだ。しかし、医学界ではこれを当たり前のこととして認めている。医学界には、「プラシ―ボ効果」という言葉がある。砂糖水を薬として飲むと 頭痛が治るといった現象を指す。心が体の反応を変えているのだ。「プラシーボ」とはラテン語で「喜ばせる」という意味だ。
医師と患者の信頼関係が良好で、患者自身の「治す」という思いが強くなると、「プラシーボ効果」が、ますます高まることがわかってきた。何より「副作用がない」というのが大きなメリットだ。われわれ医療者は、このプラシーボ効果を今一度、見直してみる必要がある。この「プラシーボ効果」とは逆の「ノーシーボ効果」というのもある。これは「否定的な思いが病気を引き起こす」という現象である。「自分は心臓病に罹り易い」と思っている女性は、そうでない女性の死亡率の4倍もあるという。
*2500年前、仏陀は「すべての人間は、自分自身の健康、ないしは病気の作者である」と説いた。また、「ポジティブな思いは、良い遺伝子のスイッチを入れる」と指摘するのは村上和雄・筑波大名誉教授だ。「 ポジティブな思いとは、他人への思いやり、つまり利他の心である。この時のワクワクする気持ちが大切であり、行動を選ぶ時は、正しいか、正しくないかより、嬉しいか嬉しくないかで選ぶべし 」と。一方、エゴや欲、怒りや不安にとらわれた行動は、その対極と言える。そのような思いは、自分の心に悪い遺伝子のスイッチを入れる。つまりは、良いも悪いも自分次第ということになる。がんに関して言えば、ポジティブな思いは「良い遺伝子」で、がん抑制のスイッチを入れる。ネガティブな思いは、逆に、がんのスイッチが入りやすい。
*鈴木秀子・聖心女子大学元教授は、心の健康を回復させる特徴として、3つのポイントを挙げている。➀運命を受け入れること。私たちを生かす大自然に感謝し、すべてを委ね、何があろうとも受け入れることだ。➁生きていることは当たり前ではない。人生はたいへんなことを自覚し、生かされているという奇跡に感謝し、生きる意欲に溢れ、毎日を送ること。➂他人や自分への愛を感じること。人とのつながりを大事にし、人に尽くしたいという強い願望を持つこと。この3つの態度が心を健康にする、鈴木先生は指摘している。言いかえれば、「運命の受容」「生かされていることへの感謝」「他人への愛」ということになる。それが人生を実り多いものにする秘訣ではないか。悔いなく、思いきり生きることができれば、最後の時期を迎えてもても、受け入れることができる。良く生きることは、良く死ぬことでもある。
=3= *科学の巨人たちが遺した言葉を紹介したい。アインシュタインは「私たちが最も美しく、最も感動をするのは神秘的なものを感受した時である。そして、これこそがすべての科学の原動力である」という言葉を遺している。ノーベル賞を受賞された山中先生と益川先生が対談で話されたのは、「人間の考えることなんかより、自然の方がずっと奥深い。そして、考えるとは、感動することである」と。このように科学の巨頭たちが揃いも揃って、知識や理性より情動の重要性を説いているのは、驚くべきことだ。考えて見れば、情動、感動という言葉はあっても、知動、理動という言葉はない。自分の感性をもっと大事にした方がいい。私の今の思いを言葉で表せば、医療現場では平均化より個別化、言いかえれば「一人ひとりの個性の違いを大事にする」ことである。心の持ちようで、体や病気が変わるのだ。したがって、今後の医療を考える時、「個別化医療」と「心を見つめる医療」、この2つがキーワードになってくると私は思う。
*がんの医療においては、医療者と患者に加え、患者の家族を加えた三者の関係を良好に保つことが重要になる。問題はがんが再発したり、進行した状況になった時である。医療者は痛みを取るなどの対症療法しかなく、次第に腰が引けていく。その一方、家族は、別離思いに苛まれ、セカンド・オピニオン探しなどに追われ、患者との対話も次第に少なくなる。そんな中で患者は自分の状態が悪くなっていくことをはっきり自覚し、後悔の念に苛まれたりする。そして何より、家族と共に最後の時を長く分かち合いたいと強く望むようになる。しかし、その一方、家族に心配をかけまいと自らの殻に閉じ籠り、つらい孤独の中で最後を迎える人が少なくない。
*最近、セラピストの資格を持つ看護師が大きな役割を果たしている。ターミナルケアの逃げようもない精神的に過酷な現場で疲弊し、現場を辞めた看護師が自分を癒すために、アロマなどの資格を取って、看取りの現場に復帰する人が増えてきたのは嬉しいことだ。このような看護師とのセラピーを通じた触れあいで、どうしようもない不安を癒されたという患者を多く見てきた私は、このような精神と技術をもった看護師に大いなる期待を抱いている。
*死と向き合うことで見えてくるものは何か。仏教は教える。死という深い悲しみをとことん見つめることにより、実は大どんでん返しが起きる。それは何か。今生きていることは当たり前ではない。感謝すべきこと。つまり、いま生かされているという奇跡への感謝に他ならない。今日、平和で過ごせたことは、当たり前ではなく感謝すべきこと。この貴重な毎日をワクワク楽しく暮らすことが旅立ちの日を、後悔なく迎えるための秘訣になるのだ。さらに仏教では、「対峙ではなく、共存すべし」とも教えている。病気の原因となった自分の考えや行動を見つめ直し、生活を改めること。悲しみの底から湧きおこってくる =4= 「どんでん返し」とは、悲嘆の極致から、感謝、愛、受容の心によって、幸せな気持ちに一気に上昇させることである。正に「どんでん返し」だ!
*神道にも「中今(なかいま)」という言葉がある。過去の後悔や未来の不安から離れ、今に集中する。今には過去も未来もない。がんがあろうとなかろうと、誰にも平等に与えられた死の瞬間・・・所詮、未来など誰にも分らない。健康であっても明日事故で命を落とすかもしれない。それが人生だ。病気の人も健康な人も、与えられたこの今の一瞬を最良とし、そして精一杯生きること、それが人生で大切なのだ。明日が来ること、それは「当たり前」ではない。そのことをわれわれは肝に銘じる必要がある。仏教でいう「生き切る」と共に、このような心境で人生を全うすること。これこそが究極の健康法ではないかと私は考えている。 (了)
- セミナーご案内
- 投稿日:2016/05/02
南海トラフ巨大地震に備えましょう 心して
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- セミナーご案内
- 投稿日:2016/04/13
社長急逝と事業承継の時の銀行交渉ポイント 【重要です】
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- ニュース
- 投稿日:2016/04/12
アベノミクス成果の逆回転と地銀の危機 2016-4
お世話になっている皆様へ
下記は、ニュースとしてお届けします。重要な内容となるのかも知れません。
◎
(景気と経済) 「アベノミクス逆回転」のメカニズム
足元の世界の金融市場における株式や為替などの展開は、一時期の不安定な状況からだいぶ
落ち着きをとりもどしています。しかし、これからどうなるか? エコノミスト・真壁昭夫
・信州大経済学部教授の見解です。
●円高が進めばアベノミクス成果が逆回転
♣ 落ち着きを取り戻した背景には、サウジやロシアなど主要産油国の生産維持が合意したこ
とにより原油価格が反発していること、EBCや日銀の金融緩和策維持の方針が明らかに
なったことがある。また、米国のFRBは3月の定例委員会で利上げを見送った。これら
が投資家に安心感を与えた。
♣ しかし、日本の株式市場は低迷が続いている。欧米や中国など主要株式市場の動きから取
り残された格好だ。日本のモメンタム(勢い)が出ない理由の1つは、昨年までの円安・ド
ル高の傾向が変化していることがある。円高の動きは、2011年秋口から堅調な米国経
済の動向を反映し円安に転じた。
♣ 日銀はマイナス金利まで踏み込み、円高の流れに歯止めをかける試みをしているものの、
今のところ、期待されたほどの効果は出ていない。今後、円高がさらに進むようだと、
アベノミクスの成果は逆回転し始めるかも知れない。短期的に見ると、為替相場を動かす
最も大きな要素は金利だ。どう動くか?
♣ ただ、ヘッジファンドなどの投機筋が円高・日本株安を狙っても、その傾向が永く続くこ
とはありえない。彼らは、基本的に買ったものは売り、売ったものは買い戻しをする。日
本株だけ売られ続けることは考え難い。ということは、短期的に見ると、「日本株だけ蚊
張の外」という状況は長続きすることはない。
●ピークアウト懸念が出てきた米国経済
♣ どこかで売り待ちになっていた部分の買い戻しが入るはずだ。そうなると日本株も徐々に
上昇余地は出てくる。現在、安倍政権は来年4月の消費税率の再引き上げを実行するか否
かを検討している。そのため、海外の著名経済学者を呼び寄せ、意見を聴取している。
一種のアリバイづくりとも見える。
♣ 市場関係者の多くは、「安倍政権は消費税率の再引き上げを延期せざるを得ない」との見
方に傾いている。それが実際に発表されると、株式市場を取り囲む状況はかなり変わる。
今年から来年にかけての駆け込み需要は期待できないが、来年4月以降の反動による落ち
込みはなくなり、株式にはプラス。
♣ 一方、金融市場にとって無視できないリスクは依然残っている。原油の過剰感は完全に払
拭されていない。中国経済の減速に歯止めがかかったわけでもない。欧州の難民問題や、
英国の国民投票など不透明感もある。また、少し長い目でみると、上昇過程がそろそろ
7年を迎える米国経済が、限界に近づく?
♣ 今年から来年にかけてピークアウト感が出るのが懸念されることだ。今後、そうしたリス
ク要因に加え、特に米国経済のピークアウトが顕在化すると、世界経済が下落傾向に突入
することが考えられる。その場合、ドルはさらに売られ、世界の株式市場は不安定化しよ
う。株価がある程度戻っても安心はできない。
(経済・景気) 日本経済、これから目指すべきこと
2000年に「日本国債」を上梓、政府の”放漫財政傾向”に警鐘を鳴らしている幸田さん、
今や日本国債の額は1千兆円を超え、このマイナス金利でまだまだ増え続きそうです。
辛口の金融評論家として定評のある作家・幸田真音氏のNHKラジオからのお話です。
●機能不全に陥っている日本の「短期金融市場」
♠ 日本経済は回復基調にあるとも言われる。実体経済の回復なきままの株高は、持力性にも
限界がある。劇薬ともいえる量的・質的金融緩和というのは、「時間稼ぎ」の対策だった。
だから、金利をゼロにして長引かせてきた間に、本来ならばしっかり規制改革するなり、
構造改革にもっと本腰を入れるべきだった。
♠ この先、ますます手詰まりになるだろう。本当にめざましい対策を打つことができるのか
どうか。本気の成長戦略と規制緩和を含む産業構造の改革を、時期を逃さず打ちだして貰
いたい。日銀が初めて量的緩和をとったのは2001年の3月19日、そのあと日本の短期金融
市場はほとんど機能不全に陥っている。
♠ そして今、長期金利の国債市場も機能不全に陥っている。これは金融政策に依存しすぎた
副作用だ。私が今、言いたいのは新しい経済の形がどんどん生まれているということ。金
融市場が根本から見直しを迫られる時代となっている。これまではモノやサービスを提供
する時代だった。
♠ そうではなく、これまでの常識とか枠を超えた新しいビジネスモデルがどんどん誕生して
いる。シェアリング。エコノミーがそれだ。ソーシャルメディアの普及を背景にしている。
つまり、「買い手も売り手になれる」「利用者もサービスの提供者になれる」というビジ
ネスだ。例えば、「ウーバー(Uber)」・・・
●新時代に備えて感度を磨いておけ
♠ タクシーの配車アプリを提供して、海外では一般の人が自分の自家用車を使ってタクシー
のような仕事をしている( 日本ではダメ )。今やウーバー・カー症候群という言葉が生ま
れている。常識の根底から覆すビジネスモデルだ。他には「エア・ビー・アンド・ビー」
だ。2008年からスタートしたものだ。
♠ 世界中の宿泊施設をネットや携帯で調べて予約できる。これがいま何と世界34000都市
190カ国に広がっている。既存の事業分野を大きく揺るがす存在になりつつある。日本古
来の経済のビジネスを大事にしつつ、どうやってこういう新しいものと共存していくか、
ということが、これから大事になってくる。
♠ 金融業界も同じ。この業界はやがて大きく様変わりするかもしれない。世界の大手銀行の
収益のうち約4割( 年間、190兆円 )が資金の決済業務から上がっている。この分野に「シ
ンペック」が新しく参入すると、このあたりの金融サービスが大きく変わってくる。携帯
電話ひとつでITの恩恵を享受できる。
♠ 人間の働き方と価値観も確実に変わる。マイナス金利がさらに進めば、おカネのそのもの
の価値観も変わっていく。だから政府は地球規模の大局的な観点に立って、産業の構造改
革とか規制改革を急がないといけない。我々も来るべき時代のために常に感度を磨いてお
くことだ。
(金融・景気) 遺産相続で預金激減する地銀が危ない
政府は「地方創生」を声高に叫んでいます。だが、華々しい表面とは別にその実体はお寒い。
増える空き家は価値が減っても遺産相続の対象になる。そんな預金が大都市圏に流出。ドミ
ノ倒しの地銀再編は避けられない。今のところ無風の近畿圏ですが。ある情報誌4月号より。
●東北・四国は再編待ったなし
♦ 地銀にとって恐怖の大津波が押し寄せようとしている。「遺産相続」だ。遺産を遺す親が
地方、それを受け継ぐ子が大都市圏にいる場合、家計資産は地方から大都市圏に流出する。
相続に伴う地銀の預金減少は避けられない。都道府県では、今後20~25年間に実に
30県から家計資産から5分の1が流出しそうだ。
♦ まず東北。明らかに銀行過剰。また、いずれも経営基盤は小さく、単独で預金流出の荒波
に立ち向かうのは難しい。次に四国。四国トップの伊予銀行の預金が丸ごとなくなること
を考えれば、とにかく多すぎる。すでに香川銀行と徳島銀行が経営統合し、大阪の大正銀
行を傘下に加え攻勢を強めている。
♦ しかし、家計資産流出の度合いが香川・徳島より大きい愛媛と高知は今のところ音なしだ。
第二地銀の愛媛銀行、高知銀行はどう動くか?次に九州。鹿児島と熊本では県内トップの
鹿児島銀行、肥後銀行が手を組んだ。各地の大名家の財産が基礎になっている所も多いが
「殿様地銀」もなりふり構っていられない。
♦ 殿様地銀でさえ危ないのだから、零細地銀は言わずもがな。今、全国で預金量が1兆円に
満たない地銀が地銀・第二地銀は20行以上もある。地元の有力信用金庫にも及ばない規
模であり、「銀行」としての存在意義が問われている。こういった銀行は、高コスト体質
という問題を引きずっている。
●県境を越える「ドミノ倒し」
♦ 参院選の「一票の格差」是正のため、鳥取と島根、徳島と高知は合区になった。選挙区と
同じく地銀経営と都道府県単位では成り立たなくなりつつある。県境を超えた広域再編が
どんどん増えるだろう。奇しくも合区の対照となった鳥取・島根では、鳥取銀行と山陰合
同銀行の動向が注目される。
♦ 鳥取銀行は県下唯一の地銀だが、ここも総資産1兆円足らず。鳥取県内の預金シェアは
29.2%で、お膝元ですら山陰合同金庫(同58.8%) に遠く及ばない。( 預金シェアはゆう
ちょ銀行を除く )名より実を取るならば、山陰合同銀行との再編は焦眉の急だ。県境を越
える経営統合は、次なる再編のドミノ碑を倒す。
♦ ふくおかフィナンシャルグループ(FFC)を例にとれば、福岡銀行が中心となって親和銀
行(長崎)、熊本銀行が同じ傘の下に入った。その結果、追いつめられた十八銀行(長崎)は
同じFFCの軍門に下り、熊本銀行=FFCの圧力に危機感を強めた肥後銀行は鹿児島銀
行の統合に走った。佐賀、大分、宮崎も同じ。
♦ いずれ「九州地銀戦争」に巻き込まれるだろう。検査局長在任中から地銀経営の将来に警
鐘を鳴らしていた森信親・金融庁長官にとって、地域金融再編はライフワークである。
マイナス金利導入に伴う地銀業績の悪化は確実であり、さらに相続に伴う預金流出懸念も
のしかかるとなれば、再編の号砲が鳴り響く。
人間の運命の九割は自分の不明による罪だ 坂本 竜馬
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- 事業承継
- 投稿日:2016/03/19
老舗優良企業を譲った(元)経営者のお話を聞きました。
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- セミナーご案内
- 投稿日:2016/03/15
「一般社団法人」を活用した会社の守り方 銀行交渉も(^_^)
「一般社団法人」を活用した会社の守り方をご紹介(^_^) 「地銀の命運と備え方」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※銀行交渉セミナー、平成17年5月を初回として、98回目の開催となります.感謝!
A)銀行返済ができなくなっても夜逃げ・自己破産ましてや自死、一切不要 / 銀行の
営業担当が喜ぶ、融資を希望する企業がつくるべき書面とは( 銀行内の融資決定者へ
の効果的武器 )/ 金融庁が銀行に掛けている具体的圧力の解説.2年後の赤字予想
銀行の実名、ビジネス雑誌に公開されています.お気の毒です、そんな銀行の末路 /
地銀の「ここまでやるか営業」( ある地銀の在阪企業へのビックリ条件提案がきっかけ
でその企業、取引銀行すべての保証人外しに成功 )/ 後継者にバトン・タッチして
いく時のリスク対策 …こんなことを今まで講師にお話頂いてきました.
B)ところで、あるキーワードにより、今までの講演内容の一部が建設的に変わりました.
本質論は、もちろん「 銀行マンの弱みを知り、手玉に取りましょう 」です.
そのキーワードとは、「一般社団法人」.
そんな大層なことか?たいしたこと、ないやん!との 声が聞こえてきそうですが、
実は、活用の方法が幾つかあるようです.
C)今回の銀行交渉セミナーは、一般社団法人を活用した、ニュースキルのご紹介がメイ
ンです.講師、今まで忸怩たる思いで、「会社・自宅から遠く離れた銀行にも口座を
もちましょう」と言っていましたが、その必要もなくなるかもしれません.海外送金
プライベート・バンクの 必要性も小さくなるかも…
全く新しいスキルとご認識頂けるはずですヽ(´▽`)/.
セミナー内容「一般社団法人」の機能性から 資産も家もオーナー経営も守りましょう!!
1 事業を守る、資産を守る -確約は控えますが、法の網の目をくぐる必要がなく
なりそうです.
2 一般社団法人の行なえる事業から構築できるスキーム例 経営者の自宅の保有
/ 個人資産の保有・運用 / 未上場企業の株式保有 〇法人も一般社団法人の
社員に.現存の株式会社のオーナーが一般社団法人の代表理事になれます.
と言うことは・・・続きはセミナーで.
3 ところで、自己資本に加算できる「資本性ローン」、ご存知ですか? 15年間は金利
のみの支払い.その後の一括返済、どうするか….手はあります.ここでは書けません
!!もう一点.「後継者のためのローン」.赤字企業でも大丈夫.でもなぜ?政府と金
融界の事情があります.知っておかれた方がかなり得かも知れません.
( ほとんど知られていないようです )
4 地銀の余命 ワースト・ランキング50とその解説.金融庁、優良でない27の地銀
を名指しをして「どこかの傘下に入るなり何とかしろ」と助言されました.地方銀行
・信金信組の窮状をご紹介します。貴社が地銀とお付き合いしていなくても貴社の販
売先・仕入先すべてが地銀・信金・信組と取引が一切ないことは考えにくいはず.
取引している地銀・信金信組が吸収される側だったら融資条件は悪化します.最悪を
想定しておくべし、です. もう一点.銀行マンを手玉に取るポイント3つとプラス
ワン( 鳥瞰図で説明します ) 金融の知恵と知識と行動が、オーナー企業・雇用・
取引先を守る!= まとめ
講師について 講師はある銀行で6つの支店の支店長と債権回収部責任者を歴任.今は、
当時の同僚と独立し、債務者側に立ち、債権回収の経験を活かしながら、主として経営者
や個人事業主の再生についての助言を行なっています.
主催者からひと言 - このセミナー講師、債務者と一緒に銀行に出向くことは致しませ
んし、( 自称・銀行交渉専門家と銀行に同行すること、極めて危険です )成功報酬請
求も致しません.
理由は簡単.銀行マン時代の銀行都合の債務者への行動の罪を軽くするためです.銀行交
渉ですが銀行勤務経験なしで行なえるはずもありません.取引先のまさかに備えるために
も健全な経営者にご参加を今回も呼びかけます.
少々のご無理をしてでもお越し頂きたくご案内申し上げます.
◎資金繰りの苦労から解放されると見える景色が全く違う - お客様の喜びの声
《 開催要項とお申し込みについて 》
☆開催日 / 4月 5日(火)18:00~20:00( 少々の延長もあり得ます )
※金融界のリアルタイムの情報提供は毎回行なっています. ☆会場 / 関西文化サロン
(阪急デパート前の阪急グランドビル19F)電話(06)6316-1577(代)
☆ご参加料 / ¥10,000.-( 税込み.価格交渉、電話で承ります.
2名以上ご参加の方もお電話下さい.ご参加料、別に定めています.
☆参加対象/経営者・取締役・管理職の方及び個人事業主.健全な間に別会社をつくる必要
性も 聞きどころ.( 一般社団法人を活用したノウハウ、活字やウェブ上での公開などで
きません. 録音もお控えください. )
☆申し込み方法/ 下記の申込書に必要事項をご記入の上、メールでお申込み下さい.
●主催・申し込み先 / Business Agency たかしまよしお MP 080-4873-5786
E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp
「 銀行交渉セミナー 」( 大阪・梅田 )参加申込書 貴社名( )電話( ) - 1 ご参加者氏名( ) 役職( ) 2 ご参加者氏名( ) 役職( )
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- 情報
- 投稿日:2016/03/14
やれば出来る ← × やれば伸びる ← ◎
今夜、「深いい話」と言う番組をたまたま観ました。 中学受験と大学受験、それぞれの
実話が紹介されていました。
ラ・サール中学を目指して猛勉強した12歳の小学生。3か月で塾の先生が驚くほどの
偏差値アップ。そのことにも注目ですが、ご家族全員が応援していた様子に揺さぶられました。
受験をし、ラ・サールから送られてきたレタックス。お母さんが「大生(たいせい ご長男
の名前)宛にきたものだから自分で開封しなさい」とレタックスを手渡したシーン。
この気遣いにズン!と来ました。
もう一つの事例は、映画「ビリ・ギャル」のモデルとなっていた先生が登場。どんな場面でも
とにかく褒める! よくそんなことを思いつくな、と感心するほど褒める! 基本は、自習。
その出来を先生方が診る、と言うことですが、理想の教育と思えました。
叱る と言う行為について「萎縮させてどうするんですか?バカじゃないですか?」と
笑顔で答えていた坪田先生。米国で心理学を学んでのスキル、ノウハウということですが、
尊厳を感じると小学生も態度が変わる。
やれば出来る、ではなく、やれば伸びる、とおっしゃったことも響きました。
よい番組を見ることができてラッキーでした!(^_^)
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- セミナーご案内
- 投稿日:2016/02/28
銀行交渉 一般社団法人を活用して 自社と資産を守れ(^_^)
会社を守る 「一般社団法人」活用法、どういうこと?加えて 「地銀の命運と備え方」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※銀行交渉セミナー、平成17年5月を初回として、97回目の開催となります.感謝!
A)銀行返済ができなくなっても夜逃げ・自己破産ましてや自死、一切不要 / ノルマ達成
に懸命な営業担当と融資認可決定の担当者の行内での心理戦解説 / 銀行営業担当が
喜ぶ書面のつくり方( 対 融資決定者への効果的武器 ) / 金融庁が銀行に掛けている具
体的圧力の解説.実はお気の毒です、銀行の経営者 / 地銀の「ここまでやるか営業」
( ある地銀の在阪企業へのビックリ条件提案がきっかけ でその企業、取引銀行すべての
保証人外しに成功 ) / 後継者にバトン・タッチしていく時のリスク対策 …こんなこと
を今まで講師にお話頂いてきました.
B)ところで、あるキーワードにより、今までの講演内容の一部が建設的に変わりました..
本質論は、もちろん「 銀行の弱みを知り、手玉に取りましょう 」です. そのキーワー
ドとは、「一般社団法人」. そんな大層なことか? との声が聞こえてきそうですが、
活用の方法が幾つかあるようです.
C)今回の銀行交渉セミナーは、一般社団法人を活用した、ニュースキルのご紹介がメイン
です. 講師、今まで忸怩たる思いで、「会社・自宅から遠く離れた銀行にも口座をも
ちましょう」と 言っていましたが、その必要もなくなるかもしれません.海外送金 プ
ライベート・バンクの 必要性も小さくなるかも…全く新しいスキルとご認識頂けるはず
ですヽ(´▽`)/.
セミナー内容
「一般社団法人」の機能性から 会社も家もオーナー経営も守りましょう(^_^)
1 事業と資産を守る - 確約しませんがが、法の網の目をくぐる必要がなくなりそうです.
2 一般社団法人の行なう事業から構築できるスキーム例 経営者の自宅の保有 / 個人 資産
の保有・運用 / 未上場企業の株式保有 〇現在の株式会社のオーナーが一般社団法人の代
表理事になれます.と言うことは…続きはセミナーで.
3 各銀行の内情を披露します.その前提で「 銀行を思いやり( もちろんポーズ 笑 )」銀行
マンを手玉に 取るポイント3つとプラスワン( 鳥瞰図で説明します )
4 地銀の余命 ワースト・ランキング50とその解説.金融庁、優良でない27の地銀を名指
しをして「どこかの 傘下に入るなり何とかしろ」と助言されました.
※ふくおかFGの傘下に 十八銀行(佐世保市)が入ることも2月26日に報道されました.
地方銀行・信金信組の窮状をご紹介します. 貴社が地銀とお付き合いしていなくても貴
社の販売先・仕入 先すべてが地銀・信金・信組と取引が一切ないことは考えにくいはず.
取引している地銀・信金信組が吸収される側だったら融資条件は悪化します.最悪を想
定しておくべし.です. 5 自己資本に加算できる資本性ローン.15年間金利の支払い.
その後….ここでは書けません.
金融の知恵と知識と行動がが、オーナー、企業、雇用、取引先を守る!= まとめ
講師について 講師はある銀行で6つの支店の支店長と債権回収部責任者を歴任.今は、当
時の同僚と独立し、債務 者側に立ち、債権回収の経験を活かしながら、主として経営者や個
人事業主の再生についての助言を 行なっています.
主催者からひと言 - このセミナーを多くの経営者に提案してきました. このセミナー講師、債務者と一緒に銀行に出向く ことは致しませんし、( 自称・銀行交渉専門家を銀行交渉
時 同行させること、極めて危険です. ) 成功報酬の請求も致しません. 理由は簡単.銀
行マン時代の銀行都合の債務者への行動の罪を軽くするためです.銀行交渉ですが 銀行勤務
経験なしで行なえるはずもありません. 取引先のまさかに備えるためにも 健全な企業の経
営者にご参加を今回もご提案致します.
少々のご無理をしてでも お越し頂きたくご案内申し上げます.
◎資金繰りの苦労から解放されると見える景色が全く違う - お客様の喜びの声
《 開催要項とお申し込みについて 》
☆開催日 / 3月 9日(水)18:00~20:00 ( 少々の延長も )
4月 5日(火)18:00~20:00 ( 少々の延長も )
※上記2つの日程ですが、ほぼ同じ内容です.金融界のリアルタイムの情報提供、毎回
行なっています.そのこともあって一月おきに参加されている経営者、士業の方もお
られます.
☆会場 / 関西文化サロン(阪急百貨店前の阪急グランドビル19F)
電話(06)6316-1577(代)
☆ご参加料 / ¥10,000.-( 喫茶代と消費税を含みます.価格交渉、電話で承り
ます.複数名でのご参加の場合もお電話でお問い合わせ下さい. )
☆参加対象/経営者・取締役・管理職の方及び個人事業主.健全な間に別会社をつくる必要
性も 聞きどころ.( 一般社団法人を活用したノウハウ、活字やウェブ上での公開などでき
ません. 録音もお控えください. )
☆申し込み方法/ 下記の申込書に必要事項をご記入の上、下記主催者のメール・アドレス
まで お申込み下さい.
●主催・申し込み先 / Business Agency たかしまよしお MP 080-4873-5786
E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp
-(切り取り線)-- 「 銀行交渉セミナー 」( 大阪・梅田 )参加申込書
貴社名( ) 電話( ) -
1 ご参加者氏名( ) 役職( ) ご参加日( / ) 2 ご参加者氏名( ) 役職( ) ご参加日( / ) 3 ご参加者氏名( ) 役職( ) ご参加日( / )
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
- ニュース
- 投稿日:2016/02/28
マイナス金利、金融界の恨み節(/_;)
(金融情報) マイナス金利、金融界の恨み節
日銀のマイナス金利導入で、混乱が広がっています。短期市場は閑古鳥が鳴き、メガ銀
は「預金増は困る」と言い、地銀は計画見直しを迫られています。証券界の「貯蓄から投資
へ」も、この荒れる相場で霞む始末。2/21日経ヴェリタス、「放電塔」( 金融記者座談会 )の
メモです。
●日銀に言いたい「撤回してくれ!」 ♠ 日銀のマイナス金利導入で、市場参加者の混乱はい
や増すばかり。金融機関同士が日々お金を貸し借りし合う「無担保コール翌日物金利」の平
均値が17日、マイナスをつけた。さぞかし盛り上がっていると思いきや、その逆。市場残高は
16日以降、4兆5000億円程度と通常の4分の1で、閑古鳥が鳴いている。
・ マイナス金利で取引するのは外銀同士ばかりで、慌てているのは国内の銀行だ。メガバンク
にとって一番アタマの痛い問題は、膨らみ続けている預金をどう制限するか、だ。融資の利回
りが下がる一方で、預金金利の引き下げは限界だ。三井住友銀行の幹部は懸念する「いらない
預金の押し付け合いが始まる」と。
・いま各行は水面下で口座手数料などの研究を始めているけれど、顧客の反発も大きいだけに
結論はすぐには出なさそうだ。一方、住宅ローン。シェアを落とし続けてきた大手銀が腹を決
め金利競争に打って出た、その矢先だった。先陣をきって変動金利型を引き下げたのは、東京
三菱UFJ銀行とみずほ銀行だった。
・ 地銀からも「来期の数字は壊滅的だ。どうすりゃいいんだ!?」の恨み節が聞こえる。収
益の低下が避けられず「中期経営計画」の見直しに慌てて手をつけた地銀も多い。「前提が
狂った!」と頭を抱え、金利などの係数を一から作り直している。大手運用会社幹部はぼや
く「日銀に撤回してくれ、と言いたい」。
●売れる家庭用金庫 ♠ 安全性の高い債券などで運用する投資信託「 マネー・リザーブ・ファ
ンド(MRF) 」が苦境に立たされている。マイナス金利が短期の公社債投信を存亡の機に追い
やるなんて日銀には頭になかったのではないか? ある証券幹部は「株価の荒い動きで『貯蓄
から投資へ』なんていうお題目は霞んでしまった」と嘆く。
・ 営業マンも新規の金融商品を勧めるどころか顧客の不安を取り除くアフターケアで精いっぱ
いだ。企業の資金調達にも支障を来している感じだ。変動金利の大手向けシンジケートローン
の組成が一旦仕切り直しになった例が相次いだ。個人投資家もこの相場波乱で打撃を被ったの
ではないかと些か心配だ。
・ カブドットコム証券では日経平均株価が760円急落した12日、「追い証」の件数が2012年以
降で最大となったそうだ。昨年までの強気相場で「リスク不感症」になっていた人も多いのか
も。逆に「マイナス金利バブル」で沸いているのが、金などを扱う企業と現金や貴金属を保管
する金庫を扱うホームセンター。
・ 島忠ではここ1カ月で前年同月の2.5倍も売れた店があったという。このマイナス金利は「劇
薬」なだけに「効用」もないと困る。19日の衆院予算委員会で黒田総裁は「金利の面ではすで
に効果が表れている」と強がったが、副作用ばかりが目立つ。開けたのがパンドラの箱かもし
れぬ…
bizagency にコメントする コメントをキャンセル
脳の働きと活性化法(^_^)
今日は、脳の活性化について。ご一読下さい(^_^)
脳そのものが解明されているのは、わずか数%で大部分はいまだに分らないという。ただ、
脳の中で最も高度な働きをし、重要な部位は「前頭葉前野」で、そこをしっかり働かせるこ
とが大切とのこと・・・古賀 良彦・杏林大学医学部教授のアドバイスです。
●脳を守る基本は「正しい生活習慣」
・ 驚くべきことは、脳細胞は日々大量に死滅、その数、凡そ10万個とか。だが、すべて
使い切っているわけではなく、その意味で脳は極めて融通性に富んだ器官であり、複雑な細
胞だ。脳は大脳、小脳、脳幹と分れていて、それぞれが140億個の神経細胞と密接に繋がり、
お互いが情報を交換している。
・ 脳は筋肉と一緒できちんと使ってあげないと働きが悪くなる。働きを失った脳細胞はや
はり減っていく。脳を守るには適切な活性化、元気にしておく必要がある。そのために小学
生時代を思い出してほしい。「早寝早起き、三度の食事をきちんと摂り、適度な運動と学習
をする」こういう生活をくり返すことだ。
・ 規則正しい生活をする利点は、昼間に体を動かし、脳をしっかり活用させること。夜は
早く休む。脳を休ませてやるのだ。地球のリズムに合わせて脳を働かせるわけだ。人間の脳
は小中学生までに殆ど出来上がる。そのために脳を上手に育てる。それには、規則正しい生
活することと、よき睡眠をとることである。
・ また、「工夫(創造・クリエート)」することも脳を育てる上では不可欠。即ち、脳の中
でも最も高度な働きをしている場所である前頭葉の前頭前野を働かせることだ。日常生活の中
でいろいろある。アドリブを入れて楽器を演奏する、将棋を指したり碁を打つ - 様々な方
法で愉しみながら脳を育てることだ。
●脳の機能をサポートする最新情報は「アラキド酸」
・ 脳は体の中で最も大切な器官なので元々、疲れないようにできている。他方、脳は体内
の様々な器官が疲れていることを信号として受け取るという役割を持っている。だから、体
が疲れているという信号を脳が受け取ると、眠気を感じたり、注意が散漫になる。その原因
の多くは睡眠。脳の健康が害されていく。
・ 脳は酸素とブドウ糖があれば十分。ただ、血糖値が低くなってくると、脳がしっかりと
働かなくなる。そんな時、チョコレートを食べることによる回復効果がある。アルコールは寝
付きが良くなり、脳の疲れはとれたという気がするが実際はダメ。やはり脳の健康は、質のい
い睡眠によって維持されるに尽きる。
・ 脳の健康維持に良い栄養素は何か。基本的に脳細胞の働きを維持するためには様々な栄
養素をバランス良くとることだ。脳の機能をサポートする栄養素として、最近、注目されてい
るのがアラキド酸だ。これが多く含まれているのが魚の脂。これは人体の中では作ることができ
ない。食事から摂るしかないのだ。
・ その他、食材に卵、レバー、肉類に多く含まれている。そこでお勧めしたいのは、薄味の
和食、それに肉あるいは卵料理を一品加えること。そして、朝、昼、晩の三食を一定の時間に
きちんと摂ること。これが脳の健康維持にはとても大事。総じて、脳の司令塔というべき前頭
葉の前頭前野の活性化こそ最重要だ。
( NHKラジオ・健康ライフより )