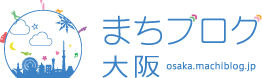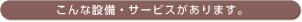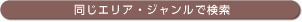スタッフブログ
- 未分類
- 投稿日:2017/10/04
NHKスペシャル 人体の神秘 心底驚きました!
タモリさんとノーベル賞学者 山中伸也教授 2人MCで始まった下記の番組、
本当に驚きました!
https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/46/2586928/index.html
詳細は、上記に譲りますが、各臓器のみならず骨まで「メッセージ物質」と
呼ばれるものを放出し、ネットワークを組んでいることが明らかになっているとの
内容です。
一例としては、高血圧患者の治療に腎臓に注射をし、改善を具現化している
こと。
しかしながら、これって理想的な組織論とも言える。 団体と組織の違いは、
マネジメントができているか否か、ということ。
人体は、各臓器が、情報を発信し合って「組織」としての人体を守っていると
言える。
健康を維持、あるいは取り戻すことを主眼にしている番組ですが、社会学と
しても見ることができるでしょう。
次回、11月 5日に期待しましょう!(#^.^#)
- ニュース
- 投稿日:2017/09/25
バリ島の火山のニュースについて
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6255242
上記のニュース、他人事とらえないでくださいね。 日本列島付近との
直接の関連性を否定している専門家はおられます。
ただ、地球全体を俯瞰して、本当に関係がないかどうかは疑問です。
夜中の地震と停電に備えて 手探りで明かりを手にするようにしておく
ことは基本中の基本です。
巨大地震の後のニュースで被災地の方の声で「 今日、こんな地震がくるとは
思わなかった 」というのが時々ありますが、こんな声を反面教師にして
いつライフラインが切れるかもしれない、という備えはどなた様もなさいます
ように…
今日は、以上です。
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- 未分類
- 投稿日:2017/09/07
前回(8月)の銀行交渉セミナーより
8月に開催させて頂いた銀行交渉セミナーのS先生のお話からの抜粋を記します。
毎回 笑顔いっぱいで深刻なお話を明るく爽やかになさるS先生、罪滅ぼしとおしゃいますが、
本当にそのようになさっています。
さて、今回のセミナーの内容から。 箇条書きさせて頂きます。
1 金融庁 森長官の続投により地銀の経営者、怒りと焦りの感情をお持ちです。
「 100行以上も地銀があるのおかしいでしょ? 7割、なくしましょ!と長官は
公の場で言っている。 近所で吸収合併にどんどん踏み切れと言っている。」
地銀の経営者のお怒り、ごもっとも。 ところで 近畿大阪 関西アーバン
みなとの3行が事実上の統合されるのはご存じの通り。
中小の経営者にご留意頂きたいのは、貴社が取引している銀行が、吸収した側か、
吸収された側か - 連れ子は可愛がられない、のと同様のことが取引銀行にも
言えます。
2 ところで、今、不況です。東京五輪までは見えない不況でも五輪後は、大不況となります。
中小の経営者、その時、笑顔でいられるかどうか!?
準備をするのは、今ですヽ(^。^)ノ
どんな準備をすべきか? 簡単に3点 ご紹介。
A 事業性評価 - 仮に今は、経常利益が充分出ていなくてもこんな将来性のある
商材がある、と俯瞰図まで書いて銀行に定期的に渡す。
銀行内の審査する側と企業周りの行員(=営業マン)の火花の散る
「打ち合わせ」が行なわれますが、具体的な資料を定期的に営業マンに
渡していると、そのことが「評価」となる。
5か年の事業計画を作成することも当たり前。但し、計画が実現化
しないといけないというガチガチのお考えは無用です(笑)
B ローカル・ベンチ・マーク
上記は企業の健康診断ツールです。 検索するとフォーマットが出てきます。
数字入力すると、あとは印字するだけ。
この数字についてですが… ここでは書くことを控えます。
C 経営力向上計画の認定を受ける
「経営力向上計画」で検索頂くとたくさんサイトが出てきます。
今年 2017年 5月末で認定を受けた企業は、21,000社。
金融庁、もっと認定を受けてほしいと言っています。
赤字でも認定を受けているケースがあります。 認定を受けると
商工中金・政策公庫から有利な条件で融資を受けられます。
また 3年間、固定資産税が半額になることもあります。
—- ところで後継者の決まっていない中小、少なく見積もって6割以上あります。
70歳前後で代がわりしていることが多いようですが、中には80歳を超えて
代表取締役社長であられて「 大丈夫! おれは元気や!!」と豪語している
方もちらほらおられますが、銀行から見れば危なっかしくて…となるようです。
ここでお伝えしたいことを又箇条書きさせて頂きます。
1 「経営者保証についてのガイドライン」があります。
これも金融庁から銀行に伝えていることですが。
○「息子が融資額が少なければ承継してもいいと言っている」と言う中小の経営者の
申し出について
金融庁の回答「取引銀行に息子さんが了解してくれる額まで債務免除してもらい
なさい」
○「廃業したくても借入があって廃業できない」
金融庁の回答「取引銀行に全額免除してもらって廃業なさい」
※上記、作り話ではありません。
2 企業の「終活」のお手伝いができるのは銀行だけでしょう( 金融庁からのおことば )
頼んでもないのにM&Aの準備を銀行が進めていることがあります。
吸収先と吸収される先が 同じ銀行の取引先であれば、銀行は、買う先・買われる先
双方から ン千万円のキャッシュを手に入れることもできるので、銀行は、積極的に
動いています。
70歳以上の経営者の優良企業で後継者が未定ならば絶好のターゲットとなります。
貴社には、「 よい物件がありますが、お求めになりませんか 」との打診があるかも。
お求めの際は、銀行交渉セミナーのS先生に 示されている具体的な諸条件を持って
相談に行かれるべし、です。 時として隠れ負債があります。
そんなことを見抜くのも専門家の力です。
( ご相談に費用は掛かりません )
以上です。
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- ニュース
- 投稿日:2017/07/20
金融庁 森長官の破壊力と地銀の憂鬱
「捨てられる銀行」(講談社現代新書)https://www.amazon.co.jp/%E6%8D%A8%E3%81%A6%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%A9%8B%E6%9C%AC-%E5%8D%93%E5%85%B8/dp/4062883694 を遅まきながら読んでいます。
この新書での 「森長官の地方創成モデルは、地銀の今までを否定している」 と言うことに
ついてその経緯などを含め、納得できることは多々あります。
そして異論として 下記の意見もあります。 ↓
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170718-00010000-wedge-bus_all
私としては、現代新書に一票を投じたく思いますが、その是非はともかく、中小の経営者に
とって地銀があちこち合併し、自社が冷遇されぬよう、手を打っておく必要があると申し上げ
たい。
ある中小企業の経営者の集まりで、「無借金経営を目指そう」と言う意見が多く出たことが
ありますが、どうやらそれは、危険なようです。
3-4行と借りて返して、借りて返してを続けながら着々と黒字経営を続けて内部留保も
確保していくこと。
その上で担保・保証人なしで 1%未満の金利で流動性を持っておくことが必要です。
いずれにしても森長官、3期目に入りました。 そのことについての記事は、下記です。
) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170706-00022532-president-bus_all
銀行の事情も知りながら、保険のつもりで借入も適度に持っておき、資金繰りを楽にして
まさかに備えておくことをお薦めします。
ちなみに次回の銀行交渉セミナーは、8月9日の午後6時からです。
お問い合わせ下さい。 takashima-358@waltz.ocn.ne.jp
以上です。
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- 情報
- 投稿日:2017/07/02
父親が90歳近い社長の中堅製造業の後継者からのメール
今日は、ことばを選びながら慎重に書きます。
大阪府内の従業員が300人程の特殊技術を持っている製造業のある会社。
現在の社長が90歳近い年齢で息子さんがいない。社内に片腕と言える役員もいない。
娘が3人いて、その長女が代表権を持っていますが、ここ5年以上出社したことがない。
次女・三女 - 経営に関わっていません。
その長女 - 50歳半ば 離婚歴のない独身 - と 15年ほど前に知りあい、2-3年に
一度お会いしていましたが、その危機感のなさにびっくり!
現社長の三女の娘( 長女からすれば姪 )が、ある大学の経営学部を4年前に卒業していて
本人は継ぐ意思があると言うことですが、高級外車を乗り回して週末は出社せずにいつもどこかに
出向いているとのこと。
どこかに経営の勉強に出向いていればいいのですが…
その50歳代半ばの長女の方に銀行交渉セミナーや事業承継のゼミナールをお薦めして
いますが、「 気持ちが落ち着いたら… その時は遅いかも知れませんが… 」とメールが
来ました。
お伝えすることはお伝えしましたし、現在の経営者にも手紙はお送りしました。20年ほど前
ですが何度かお会いしたことも( 今も経営者に )あるので、私のことを覚えてくれて
いればと思います。
いつか良くない意味で その会社がニュースになるのかも知れませんが、そのご一族とその
会社の問題です。
関わり過ぎない方がいいように思います。 諸行無常。 今日は複雑ながら以上です。
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- 未分類
- 投稿日:2017/06/20
潜在的睡眠不足の怖さ NIKKEI STYLE
○最近の関心事のひとつが、瞑想・睡眠です。
今まで私は、軽視していました。しかしながら、6月18日に放送された「NHKスペシャル
睡眠負債 寝不足で命を落とす」も驚く内容でした。
( 6月20日の深夜に再放送 )
下記、お確かめ下さい。それとマインドフルネスのことも少し知って下さい。
下記の本、私、今 4回目を読んでいます。 よろしくどうぞ!
「最高の休息法」(ダイヤモンド社)
○
自覚できない睡眠不足――「潜在的睡眠不足」の怖さ
「睡眠時間が6時間を切ると辛い」 「睡眠不足になると眠気や疲労感がひどい」
「睡眠不足ぎみだから、今週末は寝だめをしよう」
眠気、頭痛、だるさなど、誰しも睡眠不足の辛さは経験したことがある。何時間くらい眠れば寝
不足感がないか経験的に知っている。だから自分が睡眠不足かどうか知ることはたやすい、皆さん
そうお考えではないだろうか。 .
しかし、そのような“常識”は正しくないことが私たちの研究で明らかになった。
2016年10月には、「『潜在的睡眠不足』の解消が内分泌機能改善につながることを明らかに」と
いうタイトルでプレスリリースも出している。 .
現代人の多くが自覚できない睡眠不足を抱えており、しかも想像以上に心身に悪影響を与えてい
ることを示唆する研究データが得られ、皆さんに知っていただきたいと思ったからである。
今回は、この「潜在的睡眠不足」について少し深く掘り下げた解説を加えたい。 .
標準的な睡眠時間で、日中には不調なし。万々歳のはずだが…
研究の概要をご説明する。研究対象は20代の男性15名である。「適切な睡眠習慣で生活してい
る」という自信がある人に参加してもらった。実際、日中の眠気は感じておらず、事前に行った睡
眠ポリグラフ試験でも睡眠の質・量ともに問題はなかった。 .
特殊な睡眠判定デバイスで測定した自宅での平均睡眠時間は7時間22分であった。これは日本国内
の大規模調査や世界中で行われた睡眠研究でも、20代男性の標準的な睡眠時間である。標準的な睡
眠時間で、日中には不調なし。これで万々歳のはずだが、問題はこの後だ。 .
次に、9日間にわたって1日当たり12時間、完全に防音・遮光された特殊な寝室で眠ってもらった。
その間は、途中で目が覚めても寝室から出られない。そうなると被験者は普段よりも長く眠るだけ
でなく、目が覚めた後も二度寝、三度寝をする。言い換えれば必要としている睡眠が絞り出される。 .
実際、彼らは初日に12時間の就床時間のうち平均10時間33分眠った。自宅よりも3時間以上も長く
眠ったのである。睡眠不足時の寝だめに相当するリバウンド睡眠が、睡眠不足の自覚のない被験者
でも見られたのである。
その後、実験期間中に睡眠時間は日に日に短くなる。睡眠不足が徐々に解消されるためだ。睡眠時
間の減少曲線のパターンから各被験者が安定してとれる睡眠時間を算出、それぞれの必要睡眠時間と
した。平均すると7日間で睡眠時間は安定した。必要睡眠時間は約7時間から9時間にかけて分布し
(2時間の個人差)、15名平均では8時間25分であった。 .
知らぬ間に心身に負担がかかる
この結果は3つの意味で予想外であった。第1は、自宅での習慣的睡眠時間(平均7時間22分)は試
算された必要睡眠時間よりも1時間も短かったにも関わらず、自覚的には眠気も含めて全く問題を感
じていなかった点である。 .
問題を感じなかった理由として、2つの可能性がある。習慣的睡眠時間は本当に不足しているのか、
あるいは必要睡眠時間が過剰評価されたのか。その答えはどちらが健康的な睡眠時間と言えるのか
による。 .
そこで、インスリン、甲状腺ホルモン、ストレス関連ホルモンなど内分泌機能を調べたところ、
睡眠不足を解消した後には(もともと正常範囲内ではあるものの)より望ましい数値を示していた。
つまり、被験者は十分な習慣的睡眠時間を確保しているように見えるが、知らぬ間に心身に負担が
かかっていたことが明らかになったのだ。 .
ちなみに、9日間にわたって睡眠不足を解消した後に、一晩徹夜をしてもらい、その翌晩に再び
睡眠リバウンドの大きさを調べてみたが、驚いたことに実験初日のリバウンド(3時間)よりも小
さかった。このことからも自覚症状なしに積み上げた睡眠不足のインパクトがお分かりいただける
と思う。 .
予想外であった第2の点は、必要睡眠時間の個人差が2時間しかなかったことである。一方で、実
生活での睡眠時間には4時間以上の開きがある。ということは、一部の人々では習慣的睡眠時間と必
要睡眠時間との間にかなり大きなずれが生じているはずである。こ時の被験者ですら平均で1時間、
最大で3時間弱の睡眠不足があった。ましてや睡眠不足を実感している人では一体どれだけ大きな不
足分を抱えていることやら。
人間は他の動物に比較して睡眠時間をかなり恣意的に操作(削減)できる特殊な存在である。
そして一般的に睡眠不足時に削られるのは「浅い睡眠とレム睡眠」であり、「深い睡眠」はほぼ
完全に保たれる。この研究の被験者でも不足していた1時間の大部分は「浅い睡眠とレム睡眠」だ
った。 .
大脳皮質が発達した人間にとっては、神経細胞の代謝を抑える、脳を冷却する、神経細胞の刈り
込み(不要なシナプス結合の解除)や記憶の固定など、深い睡眠が必要不可欠な役割を担っている
からだろう。とはいえ、浅い睡眠やレム睡眠が不要かといえば決してそうではない。結果を見ても
分かるように内分泌機能を初めとする種々の心身機能にとってやはり欠かすことはできない大事な
睡眠なのである。短時間睡眠法の信者はこの点をよく考えてほしい。 .
週末に爆睡しても完全には回復しない
さて予想外であった第3の点は、心身機能の種類によって回復までにかかる期間がまちまちであ
ったことである。この研究の被験者では眠気は自覚していなかったが脳波上は眠気が存在していた。
この脳波上の眠気は2日目には解消された一方で、内分泌機能の回復にはより日数を要した。 .
つまり、週末に爆睡すれば眠気はかなり解消するが、その他の心身機能を完全に回復することは
できないことを意味している。ところが、現実で多いのは少し回復してはまた平日の睡眠不足を積
み上げるパターンである。そして長年にわたってこれを繰り返す。だって、週末だけでも眠気は取
れるため、すっかり回復したと思い込んでしまうから。 .
ましてや自覚症状がない人では問題があることにすら気づかず、そのためにかえって危険ですら
あるだろう。正に、この点がプレスリリースで注意喚起を促す必要を感じた一番の理由である。 .
タイトルにもある『潜在的睡眠不足』とは私たちの造語であるが、2つの意味を込めて命名した。 .
1つはこれまで説明したように「自覚できない」睡眠不足という意味である。自覚できないのは
眠気などの症状がないだけではなく、睡眠不足になるとは考えにくい「標準的な」睡眠習慣を送っ
ているという安心感のためである。
もう1つの意味は、自覚できないが故に対処行動をとらず、心身への負担が長期間にわたって潜行す
る点である。 .
数多くの疫学調査から、短時間睡眠が生活習慣病やうつ病のリスクを押し上げることはよく知ら
れている。ただ、短時間睡眠の人が睡眠不足を強く自覚しているとすれば、長年にわたってそのよ
うな睡眠習慣を続けることができるだろうか。普通は眠気や疲労のため途中でダウンするだろうし、
生活も見直すだろう。むしろ、軽度もしくは自覚できない程度の睡眠不足を長期間続けることの方
が危険ではないのか。 .
自宅での睡眠不足度の測定法
このような危険を防ぐには、前述のような手間のかかる方法ではなく、要はリトマス試験紙の
ように自宅で簡単に必要睡眠時間が測定できればよい。これは私たちが今でも取り組んでいる研
究課題だが、いまだ解決できていない。それでも研究から少しヒントが得られた。 .
必要睡眠時間を自宅で測ることは難しいが、睡眠不足度(習慣的睡眠時間と必要睡眠時間のギ
ャップ)は初日のリバウンドの大きさ(自宅よりも何時間長く寝たか)と強く相関していた。 .
自宅で睡眠リバウンドを概算するには、しっかり眠気が来てから、個室で、目覚ましをかけず、
遮光カーテンを引き(もしくはアイマスクをして)、耳栓をする。自然に覚醒してそれ以上二度寝
ができなくなるまで眠ってほしい(例えば夜0時~翌日昼すぎまで)。その夜の実質的な睡眠時間
の合計と過去1週間の平均睡眠時間との差が3時間以上なら、ふだん眠気を感じていなくても睡眠習
慣にはもう少し改善の余地があるかもしれない。 .
最後に、ショーペンハウアーの名言を紹介する(注:私なりの意訳が入っています)。 .
『 生は神からの借金であり、いずれは返済(永久の眠り=死)しなくてはならない。当座の
利息である睡眠を多めに払えば、借金完済は少し先送りされるだろう 』 .
『 潜在的睡眠不足 』の持ち主は、少額のリボ払いを忘れて、大借金をしている人よりも早
めに不渡りを出す危険性がある。 .
[著者]三島和夫(みしま・かずお) 1963年、秋田県生まれ。医学博士。国立精神・神経医療研
究センター精神保健研究所精神生理研究部部長。日本睡眠学会理事、日本時間生物学会理事、日本
生物学的精神医学会評議員、JAXAの宇宙医学研究シナリオワーキンググループ委員なども務めて
いる。『8時間睡眠のウソ。日本人の眠り、8つの新常識』(川端裕人氏と共著、日経BP社)、
『睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン』(編著、じほう)などの著書がある。 .
日経ナショナル ジオグラフィック社
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
6月7日の銀行交渉セミナーの内容の一部(*^-^*)
S先生、この日も絶好調でした。人数が少ない時ほど絶好調! 主催者としては
複雑です・・・ 汗 それはそれとして徳積み・罪償いのS先生のお話の一部を
ご紹介。 箇条書きさせていただきます。
1)自己資本比率20%を超えていたら、担保・保証人を銀行に外させて当然。
借り入れている銀行に定期預金していたら、上手に少しずつでも解約すること。
借り入れしている銀行への定期預金、銀行は自分のものと思っている。
2)「ローカルベンチマーク」- 検索してください。エクセルのフォーマットに
数字を入力するとグラフができます。これと貴社のビジネス・モデルの俯瞰図が
あれば銀行への資料となります。もちろん、交渉を有利に進めるための。
(a)「中小企業等経営強化法」この法律に基づく経営工場計画の認定、今年の3月末で
やっと18,000社。金融庁はもっと取ってほしいと思っている。
国内に240万社以上あるはず。リスケをしていてもこれを取っていたら
銀行の態度が変わります。一定額以上の投資で3年間 固定資産税が減額
されることなど、小さい、小さい!
政策公庫の金利が下がることもあり、他行はそれにならうことになる。
もちろん、プロパー融資で。
(b)「経営保証ガイドライン」- 借入が1億あって息子が承継できない、と
言っている。8千万、銀行さんが諦めてくれたら、息子は承継を考えると
言っている。銀行さん、8千万の免除をしてくれるだろうか - こんな
ご要望に応えよ!と金融庁が銀行に出しているのが、ガイドラインです。
(c)事業性評価 - 金融庁が各銀行に「各企業の将来性に融資せよ」と
言っています。ある事例。
ある企業の事業性評価について。ある銀行が兵庫県活性化協会に将来性の
評価を依頼。 するとその企業に紹介を受けた ある中小企業診断士が、
その企業にやって来て、2時間の評価を与え、融資が決まった - 額は
ここでは書けませんが、その企業の経営者、ニンマリ
銀行、上記 abcの揃っている企業を支援します。金融庁から苦言を受けない
ために( 真に奇妙な話ですが、リスケしていても一期の赤字企業でも
abcが揃っていれば強気で銀行と迎え合えます )
2)今、地方銀行の数は 105.中長期的には 1/3にはなるでしょう。
3)資金量1兆円未満の地銀・信金は、おそらく…( 書きにくいです ここでは )
4)金融庁長官 森氏 - 続投が決定。金融界に激震。森語録「融資額をノルマ
にするのは間違い」「銀行は、経営指導すべき」「債権放棄先、リスケ先を
そう指導しているかレポートを出せ」「地銀は、首都圏・近畿圏などに出向いても
いいけど、地場の企業の支援分だけを金融庁としては評価します」「手数料の率の
高い金融商品、まかりならん!( NISA 投資信託 生命保険を含む )
※銀行にしたら何をどうしたら ええねん!? そう叫びたい状況にあります。
専門的になりますが下記のニュースもお確かめ下さい。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51609
5)相続税対策として銀行が土地を持っている人に提案していた、アパート・ローン。
金融庁からストップがかかりました。「バブルの時と同じこと、しなさんな!」
そんなことかも知れません。今、仕掛かっている物件、どうなるのでしょうか?
6)りそな銀行が中心となって 関西アーバン 近畿大阪 みなと の 3行の
業務効率化が進みます。 想定される早期希望退職者を募るその数は…。
7)日本型融資を続ける銀行は、金融庁に目を付けられます。日本型融資とは
何か? 担保・保証人を債務者に求める融資のことです。
8)「事業継承マニュアル」
経営者の平均年齢 約65歳 経営者が社長を引き継ぐ平均年齢 約70歳
そして、後継者の不在:未定が 64%。
金融庁の指導で各銀行に 廃業支援チームが組織されています。融資先の企業の終活
シナリオを各銀行が書いている - だから頼んでもいないのに後継者未定の優良な企業の
経営者に「売り先があります」と提案をしています。
M&Aが銀行にとって最も稼ぎやすい。事情があってM&Aがむずかしければ事業譲渡の
お手伝い。
借入額が多すぎて廃業できない - 銀行が債権放愛度棄を申し出ることもあります。
金融庁が、債権放棄した額を出すように各銀行に指示を出していますので…。 これも
経営保証のガイド・ラインです。
○以上、セミナー内容のほんの一部を記しました。次回は、8月9日の18時から梅田での
開催となります。お問い合わせ下さいませ。たかしまよしお 080-4873-5786
では!
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- 未分類
- 投稿日:2017/05/31
銀行対策・資金繰りについてのよくあるご質問(^.^)
今まで12年以上にわたって開催してきました銀行交渉セミナー。
多くの方をお救い出来ているようです。「助かった~」と多くの相談者はおっしゃいますが、
中には講師の助言と真反対の動きをされ、悲しい現実を自ら呼び込んだ方もいらっしゃいます。
率直に申し上げたいことがあります。
講師、罪償いで債務者の応援をしていること、本当です。貴社にとって大切な、貴社のお取引
先で「資金繰り、まずいかも」と思える企業があれば場合によっては、セミナーに参加せずとも
個別の相談をお受けしています。
初回、もちろん、無料です。半年経ってもう一度の場合、事前におっしゃって下されば無料です。
料金の有無にかかわらず、講師、真摯に助言されます。私、この10年少々の間に約50名以上の
経営者を講師の事務所にご案内させて頂きました。
セミナー受講者からのご依頼でセミナーを受けずに個別のご相談を希望された方の数です、50
名と言うのは。
さて、銀行対策・資金繰りについてのご相談の代表的な内容を記します。主に資金繰りを大きなテーマとしている企業の場合です。
〇
1 創業者の奥様の事例。政府系金融機関から呼び出された。2年前に創業者でもある先代社長が
6千万円の融資を受けていたが、事故で急逝した。長男がやりくりしてギリギリの生活をしてい
る。金融機関から6千万円を返せと言われても返せない。どうしよう? と講師に相談。
※ 実はこのお話、ハッピーエンドとなりましたヽ(^。^)ノ
2 業績悪化から立ち直りつつある状況で、銀行に支援を打ち切られた。
3 計画性なく融資を受けていたある企業。無駄遣いし、経費増加で赤字に転落、銀行からの繰
り回し貸し付けが止まった。企業の突然死に銀行マンの罪の意識はありやなしや…。
4 現場の営業マンの「融資できます」を信じないで下さい。融資を認める本部や保証協会審査を
通らなかった時、営業マンはこう言います。「支店ではやりたかった」「私はやれると思った」
- 融資を当てにして進めていた案件が頓挫。こんな時、どうする?
5 手形貸付。通常、担保は取りませんが定期預金を担保に手形貸付をしています。それって、自
社のお金ですよね? 変だと思ってください。
6 銀行を信用している経営者が今もおられます。30年間、一度も返済が遅れてないから銀行か
ら信用されている? 早く目を覚まされますように…
7 実例。売上40億円が15億円に激減。借入20億円。債務過多。銀行は不動産担保を処分
して身軽になることを提案してきた…。任売で銀行は回収額を決定したかっただけ。もし、
そうしていたら他行も回収に走ります。このケース、講師、どう助言し、解決したか?? 主
力と言えども信用すること、危険と心得て下さい。
8 「経営者がお人好し」だと銀行は、担保・保証人の追加を要求してきます。事例はいっぱい!
実は、金融庁 担保・保証人を銀行に取ること、勧めていません。レポート、お見せできます。
9 地銀の統合が進んでいます。銀行の持つ不良債権の処理には公的資金が使われます。吸収される
側の銀行の不良債権先は、切り捨てられます。知恵があれば幸運と言い切れます!!
どういうことか?
10 金利引き上げ交渉 - 銀行は、「金利変更依頼書」なるものを金利の引き上げの際に持って
きます。変でしょ? しかし、断ると融資を受けられなくなるかも、と言う懸念から受ける 経営
者が多いようです。どうする?
11 「預金との相殺をして金利負担を軽減しましょう」 - この提案を裏読みすると…。
キーワードは、期限の利益喪失。銀行提案、鵜呑みにしないでください。
12 担保処分だけで収まらず、任売した固定資産の売却損が想定より大きくて債務超過が膨らみ、
支援ができなくなった - こんな場合、どうする?
13 手形貸付の返済を迫られたら? 折り返しは約束されていません。
「 一旦 一括返済してく ださい。3日後に再実行します。」 - 責任を本部に押し付けて実行
されない事は多々あり ます。
一括返済を断って、当座の預金と相殺された企業もあります。どうする?
14 融資と引き換えに積立を要求する銀行マンが時々います。違法行為です。
正面からでなくどう断るか?
15 経営者の報酬があまりに低いと銀行はこう思います。「 すごく苦しいんですね? 」
ではどうする?
16 銀行からの提案。国債 投資信託 定期預金 保険 - すべて断るべし!
断り方、あります。
※思いつくお取引先があれば、まず私にご連絡相談ください。
費用は掛かりません。私、 講師の罪滅ぼしの姿勢に共感していますので
たかしまよしお 080-4873-5786
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- セミナーご案内
- 投稿日:2017/05/31
次回の銀行交渉セミナーヽ(^。^)ノ
今の景気。芳しくないとお応えになる経営者が多いです。備えましょう、地震のみならず、
財務上の危機に…。 1人で考え込まれることがありませぬように!
○
( 銀行交渉セミナー )金融庁の地銀・信金への無理難題の内容ご紹介と 経営者の打つべき手
※銀行交渉セミナー、平成17年5月を初回として、107回目の開催.感謝!
A)地方の人口減少による地銀・信金の弱体化 / 中小及び小規模企業の3割に後継者がいない
こと / 国と地方公共団体の税収が減少していること - 実はこれらの事情が金融庁の方向性を
大転換させました.金融庁の金融機関へのお達しの1つ 「廃業支援をし、M&Aを加速させよ!」
B)昨年7月に施行された「中小企業等経営強化法」.2017年3月末日で18,242件が
認定件数となりました. 「 中小企業等経営強化法 認定 」で検索なさって下さい.
認定を受け、一定の条件の設備投資により固定資産税が半額 - そんな内容も入っています.
C)そして時々耳にする「事業性評価」. 財務データや担保・保証に必要以上に依存すること
なく、取引先企業の事業内容や成長可能性などを各銀行が独自に 評価して行う融資のこと.
これが何を意味しているのか?
各銀行の皆様、金融庁のお達しから緊張感(大きなお悩み)が膨らんでいます.中小企業経営
者の行なうことは? 知恵と知識があれば今、チャンスです.
D)今回の銀行交渉セミナー、国と金融庁の指導により、如何に金融機関が悩んでいるかをご理解
頂き、自社はどう具体的に動くべきかのヒントをお示しすることを目的にします。
「中小企業等経営強化法」の認定、当初より取りにくくなっています.しかし、使わぬ手はない!
セミナー内容「金融庁の金融機関への指導内容」を解説.良い意味で逆手に取れるかも?
1 「 中小企業等経営強化法 目的 」で検索し、経産省や中小企業庁のコメントをご確認下さい.
省や庁、後継者不足解消の一手として中小企業の付加価値向上を具現化しようと考えています.
一方で、金融庁は各銀行に廃業支援チーム設置を呼び掛けています.実は矛盾しません.
2 地銀の苦悶.人口逓減の道県の地銀は首都圏・近畿圏等への出稼ぎを余儀なくされています.
しかし、金融庁は地銀に地域にどれだけ貢献しているかを報告せよ、とお達しを出しまし
た.出稼ぎ先での利益は評価しないとも.また業績の奮わない企業の指導も銀行の役目と言い
出し、挙句の果てにはリスケ先の指導の状況をも知らせるようにと…。
信金・信組は地場を離れることが出来ずに金融商品販売での手数料稼ぎを試みましたが
ここにも金融庁の網が.
地銀と信金の将来を想像します.吸収・合併が進むのはもちろんですが、融資先への影響は?
3 そのプロパー融資獲得のために活用できるのが「 中小企業等経営強化法 」です.
認定を受けると政策公庫と商工中金からの融資を有利に受けられることが明記されています.
中小企業等経営強化法の認定を受けると…. リスケをしていても認定されることがあります.
また、製造業企業が一定額以上の設備投資を行なえば一定期間、固定資産税が半額免除.
裏事情.政府も焦っています.中小企業の技術継承に.大企業にも影響を及ぼしますから.
4 為替と株ですが、世界中、安定しているところがありません.政府の考えていること、中小
企業に出来そうなことを講師、大胆に想定し、銀行との付き合い方を具体的に提言します.
金融の法律知識と 金融についての知恵ある具体的行動が、自社と取引先を守る!= まとめ
講師について
講師はある銀行で6つの支店の支店長と債権回収部責任者を歴任.今は当時の同僚と独立し、債務
者側に立ち、債権回収の経験を活かしながら、主として経営者や個人事業主の再生についての助言を
行なっています.
「自死やむなし」から「健全経営」へ 助けられた経営者、数知れず.セミナーご参加が2‐3名の
こともありましたが、講師は真摯に10年以上語り続けています.
主催者からひと言 - このセミナーを多くの経営者に提案してきました. このセミナー講師、
債務者と一緒に銀行に出向くことは致しませんし、
( 同行交渉、銀行は怒り出します.ましてや自称・銀行交渉の専門家は訴えられることも… )
成功報酬の請求も致しません.
理由は簡単.銀行マン時代の銀行都合の債務者への行動の罪を軽くするためです.
銀行交渉ですが銀行勤務経験なしで行なえるはずもありません. 取引先のまさかに備えるため
にも健全な経営者にご参加を今回も呼びかけます.
少々のご無理をしてでもお越し頂きたくご案内申し上げます.
◎資金繰りの苦労から解放されると見える景色が全く違う - お客様の喜びの声
《 開催要項とお申し込みについて 》
☆開催日 / 6月7日(水)18:00 ~ 20:00 ( 講演100分質疑応答20分 )
※金融関連の時事情報は、その都度ご提供.毎回お越しになる方もいらっしゃいます.
☆会場 / 関西文化サロン(阪急デパート前の阪急グランドビル19F)電話(06)6316-1577(代)
☆ご参加料 / ¥10,000.-( 消費税を含みます.価格交渉、お電話で承ります.)
◎
☆参加対象/経営者・取締役・管理職の方及び個人事業主.健全な間に別会社をつくる必要性も
聞きどころ.( この内容、活字やウェブ上での公開などできません.録音もお控えください. )
☆申し込み方法/ 下記の申込欄に必要事項をご記入の上、主催者のメアドにメールでお申込み
下さい。
●主催・申し込み先 / Business Agency たかしまよしお MP 080-4873-5786
※資金繰りのテーマについて緊急のご相談があればお電話下さい.初回無料.ご遠慮なく.
E-mail:takashima-358@waltz.ocn.ne.jp
—–( 切り取り線 )‐‐‐「 銀行交渉セミナー 」( 大阪・梅田 )参加申込書 ‐‐‐‐‐‐
貴社名( ) 電話( ) -
1 ご参加者氏名( ) 役職( )
2 ご参加者氏名( ) 役職( )
西森賢作 にコメントする コメントをキャンセル
- 未分類
- 投稿日:2017/04/29
遺品整理セミナーを開催させていただきました
昨日、屋宜講師による遺品整理セミナーを主催させていただきました。
高齢者の一人暮らしの方の亡くなり方の一つ。
モノいっぱいの部屋で歩くこともままならず、つまづいて 頭を打って 足の骨にひびが
入っていて動けなくて そのまま息を引き取られた方がいたそうです。
ご近所さんが、何かおかしい( 表現は控えます )と感じて、警察に連絡し、保健所も
呼んで、死亡が確認されたとのこと。
屋宜講師は、ご遺体が搬出された後のモノの整理をなさったとのことですが、モノが多すぎる
危険を思い知らされる内容にご参加皆様の空気が変わりました。
次回は、5月13日に開催させていただきます。
あらためてご案内申し上げます。
以上です。